2010年07月20日
3つめは公私日記

残堀川を登ると滝口というところがあり、

農業試験場の西側に

立川市歴史民俗資料館があります。
奥多摩街道かな、右側の道は。
中世の立川は、武士の時代で
合戦もあったようです。
武蔵武士、関東武士と言っても、普段は農業をしながらなので
戦いは田畑などではやらなかったそうです。
広い所、、多摩川の河原が選ばれたのはその理由と
川は攻めるにも守るにも格好の地形なので
できれば河原が欲しいと。

板碑も数点展示していました。
立川府中調布などは、武蔵板碑という秩父の緑泥片岩を使っているので
雨に当たるとみどりになるんだそうです。
諏訪神社の獅子頭もありました。
300年以上もの歴史のある獅子舞なんですね。

夏に立川駅のコンコースで獅子舞をやっていて
なんで、夏に?と思っていましたが8月にやるんだそうです。

立川の歴史を知るポイントの3つ目は、公私日記。
柴崎村の名主であった
鈴木平九郎氏が、書かれたものです。何と23冊!
幕末のころの様子を知ることのできる、貴重な古文書です。
ペリーの来日にどれだけ驚いたか!
立川までそのニュースが届くのに何日だったと思いますか?
ラジオもテレビも携帯もない時代です。
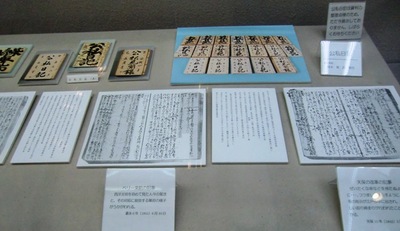
この公私日記を判読している方々が活動中です。
どんなことが書かれてあるのか
それによって立川のことだけでなく知れそうです。








